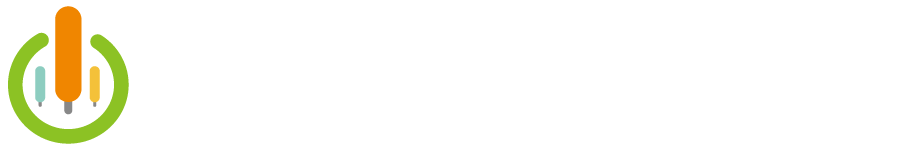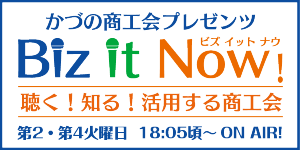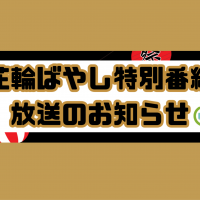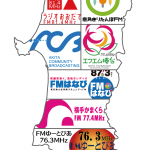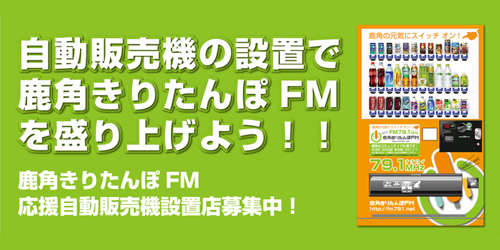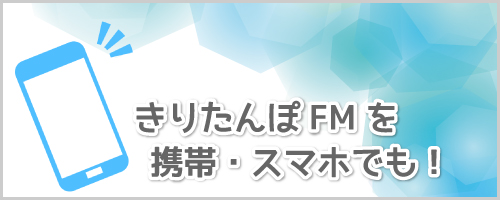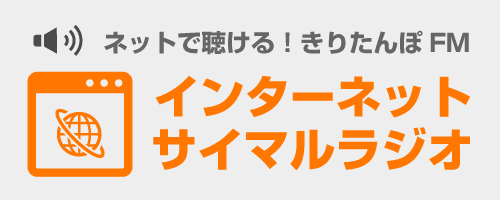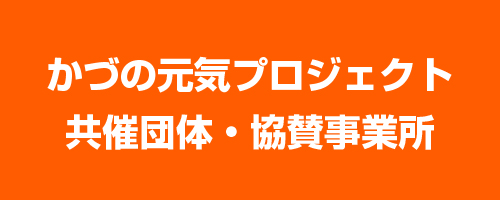江戸文化が香るいなせな鹿角市の伝統芸能「花輪の町踊り」がことしも始まり、踊り手たちが、秋の夜に町を渡り歩きながら楽しんでいきます。
花輪の町踊りは、商家のだんな衆が親しんだ江戸の盛り場のはやり歌と踊りを基に、昭和30年代に盆踊りに替わって町の通りで踊られるようになったもので、秋田県の無形民俗文化財に指定されています。
「花輪祭の屋台行事(花輪ばやし)」の終了後から中秋の名月までの間、花輪ばやしに参加する町内を巡って行われていて、ことしの初回が23日夜に舟場町でありました。
子どもたちが踊りを楽しんだあとの午後8時ごろ、浴衣やはんてん姿の大人たちおよそ70人が舞い始めました。
伝承されている12曲の踊りはストーリー仕立てになっていて、春の農作業から豊作の喜びまでを表現した「おやまこ」や「どっこいしょ」などの曲が順に踊られました。
踊り手たちは、通行止めになった通りで輪になり、保存会の人たちの歌と演奏に合わせて、手数が多く、軽快さが特徴のいなせな舞いを楽しんでいました。
親子で参加していた地元の50代の母親は、「せっかく覚えた踊りなので、忘れないようにと参加していますが、30年ぐらい続けているのは、楽しいからなのだと思う」と話していました。
また、若い踊り手が少ないなか、帰省して参加していた東京の20代の女性は、「古里での楽しみが増えるので、地元の人も、市外に出ている人も楽しんだ方がいいと思う」と笑顔を見せていました。
花輪の町踊り保存会の菅原廣志会長(76)は、「花輪の町踊りは12曲もあるので、覚えるのも、踊るのも楽しいと言ってもらっている。大勢に踊りに来てほしい」と話しています。
ことしは来月13日まで残る6つの会場で開かれる予定で、夏の祭りで活気づいた花輪の街に、秋への移ろいを告げていきます。

(写真はクリックすると見られます)