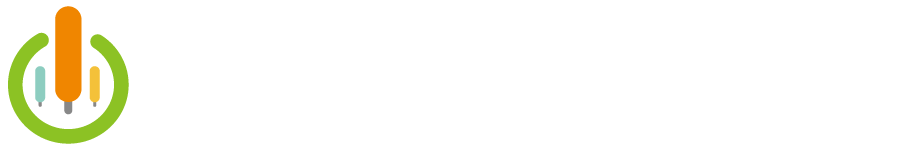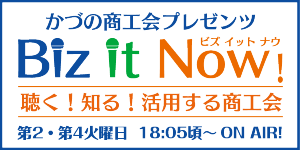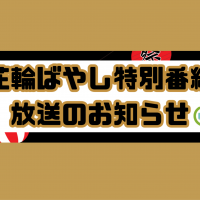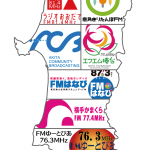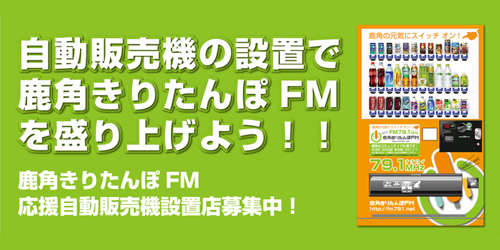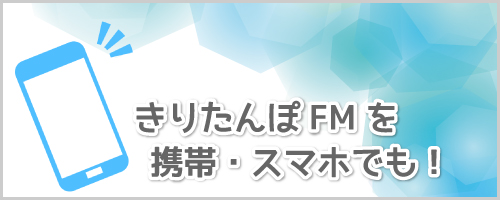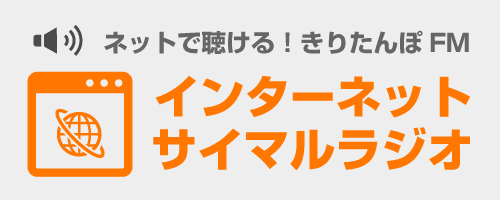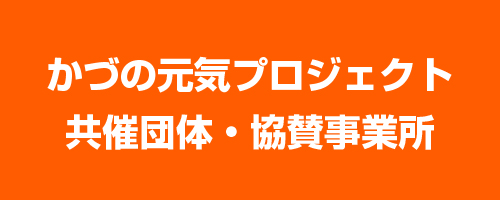流れるような手さばき、足さばきが特徴の鹿角市の伝統芸能「毛馬内の盆踊(ぼんおどり)」が始まり、晴れ着を着た踊り手たちが優雅に舞っています。
先祖の供養で踊られている毛馬内の盆踊は、およそ450年前、戦から帰った兵士たちをねぎらって行われたのが始まりと言われ、国重要無形民俗文化財とユネスコ無形文化遺産に指定、登録されています。
コロナ禍の中止や短縮を経て、おととしから通常開催となり、市によりますと去年はおよそ1万4千人の人出がありました。
初日の21日午後7時半ごろ、着物を着て、手ぬぐいで頬かむりをした踊り手たちが、会場の毛馬内の商店街に集まりました。
そして、太鼓と笛のはやしで踊る「大の坂」と、歌に合わせて舞う「甚句」が順に行われ、踊り手たちは流れるような手さばき、足さばきでゆったりと舞っていました。
雪よけのひさし「こもせ」が連なる古風な町通りで、かがり火を囲んで優雅な舞いが繰り広げられ、観覧者たちが風情を楽しんでいました。
去年4月の統合で高校が地元からなくなったものの、新しい高校でも毛馬内の盆踊に携わる同好会があり、ことしは6人が踊り、太鼓、笛、そして歌で参加しました。
踊り手を務めた高校3年の男子生徒は、「伝統芸能を受け継ぐ一人になりたいと思い、参加を始めました。腕の動きを滑らかにしようとしているので、うまく踊れた時にうれしい」と話していました。
保存会の馬渕大三会長(72)は、「高校が毛馬内からなくなっても、こうして参加してくれているので、子どもたちに教え続けてきたかいがある。少子化のなかでも子どもたちが踊りにふれる機会をつくり、後継者を育てていきたい」と話しています。