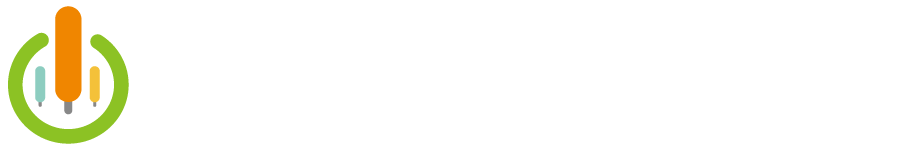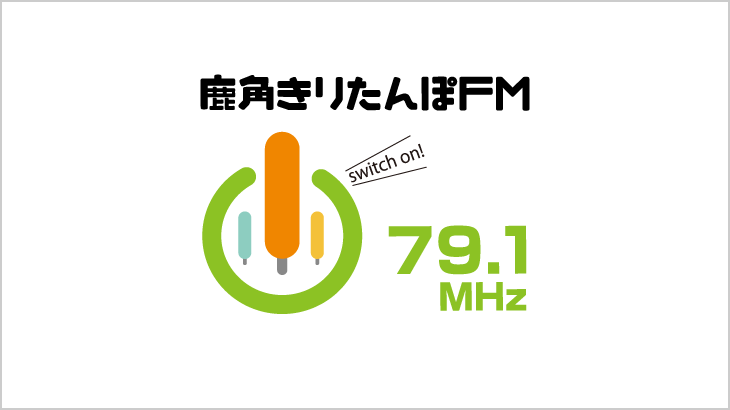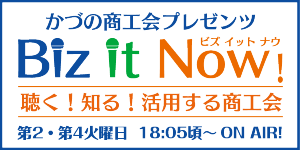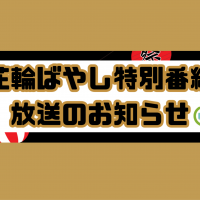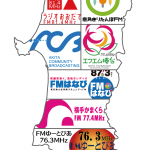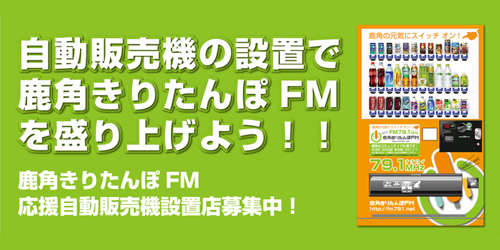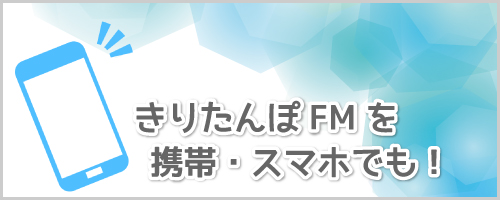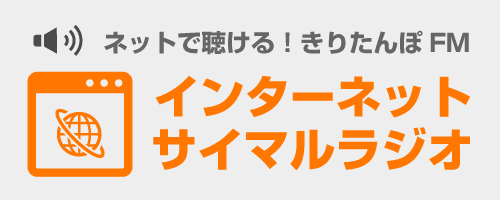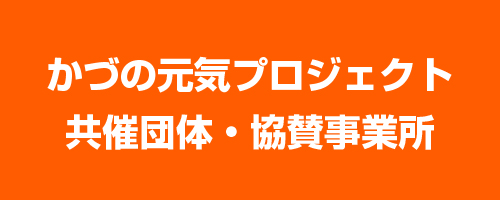鹿角市の郷土史家が「花輪祭の屋台行事(花輪ばやし)」の新たな論文を出版し、地元の人たちに語られてきた京都や平泉からの移入説とは異なる、江戸を手本にしたという見解などを示すとともに、神事である祭りの本質を訴えています。
論文を出したのは、花輪谷地田町の郷土史家で、市歴史民俗資料館の館長、藤井安正(やすたか)さん(69)です。
花輪ばやしの本格的な研究を10年ほどしていて、去年出版したものに加筆、修正した論文を先月出しました。
地元では従来、京都や平泉からの移入説が語られてきましたが、藤井さんは、江戸の祭りやはやしが手本になったと指摘しています。
理由の一つは屋台です。江戸時代に文化の中心が京都から江戸へ移ったあと、江戸独特の山車が造られるようになっていて、花輪ばやしのそれは京都のものと違い、江戸とその周辺の屋台に近いとしています。
はやしについても、伝承曲のいくつかが、関東で発展した寄席のはやしに似ているものがあることなどを指摘し、根底には京都の祇園ばやしがあるものの、江戸に伝わり、発展したものが手本になったとみています。
また起源については、平安時代から伝わるとする従来の説に異論を唱えていて、理由の一つとして、鹿角は当時、自然災害や紛争が続いていたことを挙げ、文化的な要素を受け入れ、醸成、開花する地力は整っていなかったと考えています。
そのうえで、はやしという音楽を整えたり、豪華な屋台を運行させるには、文化を吸収し醸成する力や、財力が必要だったとし、鉱山を背景に富豪が現れた江戸時代中期との説を示しています。
いっぽうで藤井さんは、現在の祭りが本質から遠ざかっていると警鐘を鳴らしています。
論文のなかでは、「花輪の神をまつる行事として行われ、神への感謝と畏敬の念が存在していたが、明治期以降、薄れ、観光化、イベント化が進んだ。祭りを引き継いでいく子どもたちのためにも、真の目的とこれまでの変化を再認識し、神への感謝と畏敬の念をもって継続していかなければならない」と訴えています。
また駅前行事の桟敷席について、観光客への便宜が図られたいっぽうで、今まで楽しんできた地元の人を遠ざけ、また若者が減少するなかで大きな負担を強いているとし、「解決策を見いだすのがいまの課題ではないか」と提案しています。
藤井さんの論文は、市の図書館で見ることができるということです。