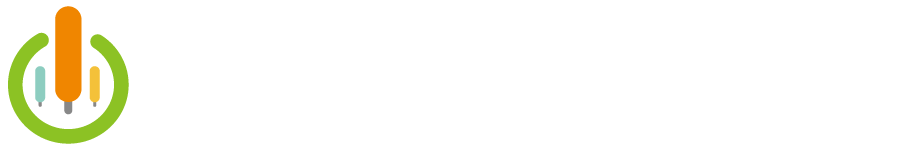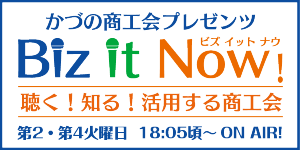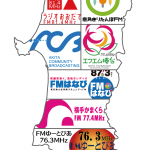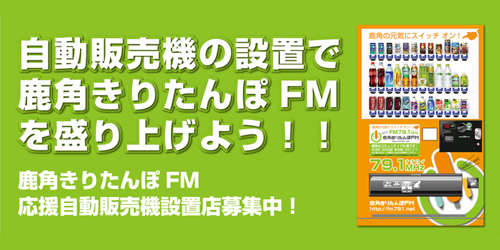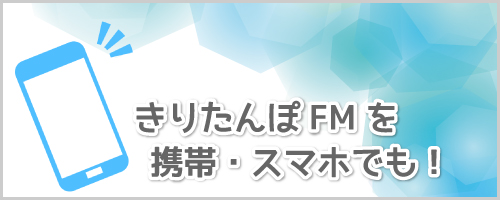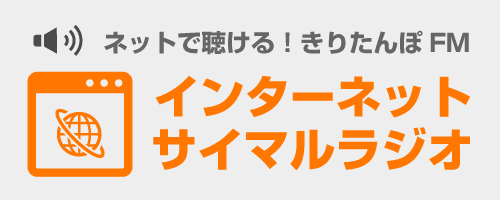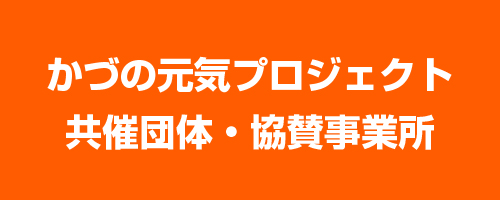鹿角市の伝統行事「花輪ねぷた」の開催が迫るなか、地元の博物館では、起源や目的などを紹介する企画展が開かれています。
花輪ねぷたは、大太鼓を打ち鳴らしながら、武者絵などが描かれた大型の絵灯ろうとともに町を練り歩いて眠り流しをする七夕行事で、毎年8月7日から2日間開かれています。
これを取り上げた企画展が、花輪横町(よこまち)の市歴史民俗資料館で開かれています。
企画展では、ねぷたは「眠たい」がなまったものが語源で、青森と秋田に多く分布していて、夏の農繁期に、眠気が引き起こすけがや、異常気象などを追い払う眠り流しと、中国から伝わった、裁縫の上達を祈る七夕が一緒に行われるようになったものと紹介しています。
花輪では、明治時代にはすでに行われていたことを示す文献が地元で複数見つかっていて、当時から掛け声に合わせて太鼓と笛が演奏されていたことや、今はない、高さ12メートルの灯ろうも出されていたことが、展示資料から分かります。
また、展示されている古い写真からは、商店街の両脇に、長さ4、5メートルの吹き流しが数多くつるされていた光景や、今はほとんど見られない、縦横3、40センチほどの子ども用の王将を子どもたちが持って練り歩いていた様子を伺い知れます。
そして、「花輪ねぷたが意味するもの」と題したコーナーでは、お盆に先祖を迎える前に、ねぷたの眠り流しで身を清めるという重要な位置づけを解説しています。
資料館の藤井安正(やすたか)館長(69)は、「今も受け継がれている花輪ねぷただが、単に繰り返すのではなく、起源や目的を踏まえることで、祭りや自分の町への愛着が高まると思う。大事なことを伝承してほしい」としています。