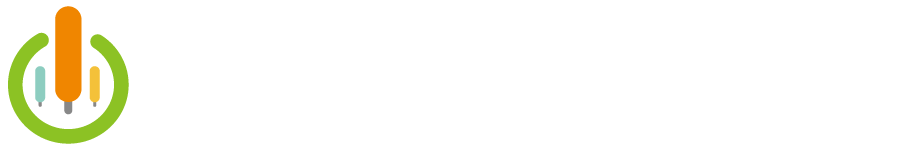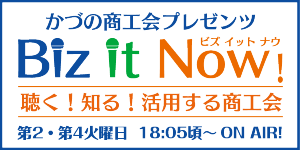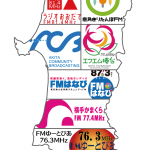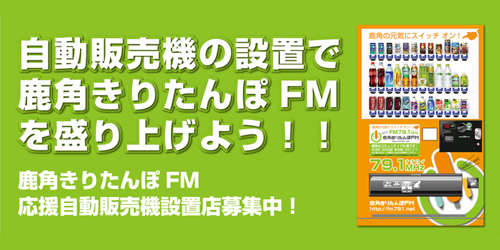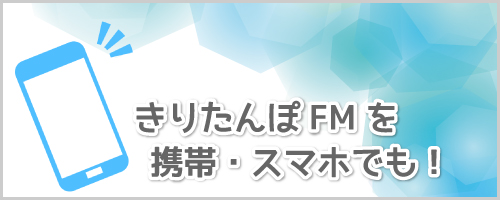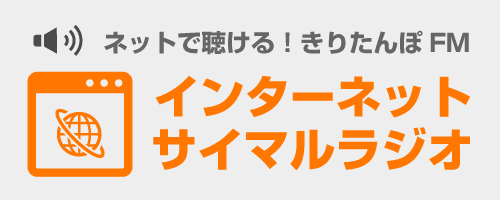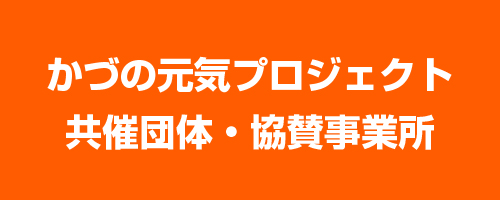明るい囃子(はやし)にあわせ山車がパレードする小坂町の伝統行事「小坂七夕祭」が3日まで2日間、行われました。コロナ明け以降減っていた山車が増えており、新たに参加した若者などが満面の笑みでわが町の祭りを楽しんでいました。
小坂の七夕祭は、鉱山が栄えた明治末期ごろ、鉱夫たちが故郷の祭りをしのび始めたと言われ、現代の町にとっても夏最大の催しです。
祭り2日めの3日夜は合同運行が行われ、立体的な人形型のものや、美人画を施した灯ろう型のものなど、光で彩られた7台の山車が町中心部の通りに集まりました。
そして子どもや若者たちが楽しそうに、「イヤサカサッサー、ホーイホイ」と掛け声を上げながら、山車を引いたり囃子を演奏したりしていました。
コロナ禍前に10台ほど出ていた山車は、コロナ明け以降、4台のみの状態が続いていたため、町が山車の制作などに関する支援を増やした結果、ことしは2つの新規参入と1つの再開がありました。
そのうち同級生を中心とした「祭好會、鉱山ノ鼓(さいこうかい・やまのこ)」は、参加していた山車がなくなった人や、祭りへの参加の道を探していた人たちで結成されました。
代表の木村優大(ゆうだい)さん、26歳は、「子どもの時からこの祭りが好きだったが、東京にいた時に山車が減っていると聞き、祭りをなくするわけにはいかないと考えた」そうで、Uターンとともに会の立ち上げに奔走しました。
若い人を増やすために山車制作などへの支援の拡充が必要だと、町長に直談判し、また同級生に参加を呼びかけると、「実は参加したかった」と次々集まった人が30人ほどに上りました。
あこがれていた人形型の山車の制作に挑戦し、何度も挫折と壁にぶつかりましたが、「みんなが毎日来てくれたからここまでこられた」と、一丸による完成に涙ぐみました。
そして迎えた合同運行では、木村さんとメンバーたちが、うれしさを爆発させるように盛り上がっていました。
実は山車造りの陰には、別の自治会の若手山車職人の協力がありました。「先輩に助けてもらってここまで来られた。次に新しい人が祭りをやりたいと言ったら、今度は自分たちが協力したい」と考えています。
そして、「若い人の参加がなければ、祭りは次に続かない。町が頑張ってくれたし、住んでいる自分たちも頑張りたい」と意気込むとともに、「この最高の達成感を、小坂の多くの若い人たちに味わってほしい」と話しています。

(写真はクリックすると見られます)