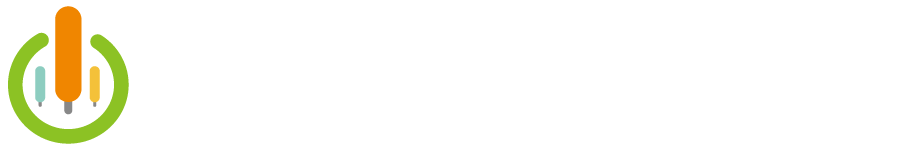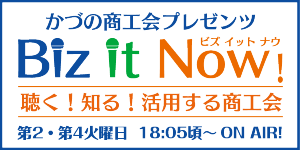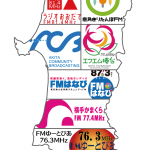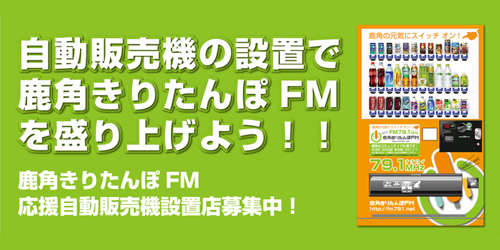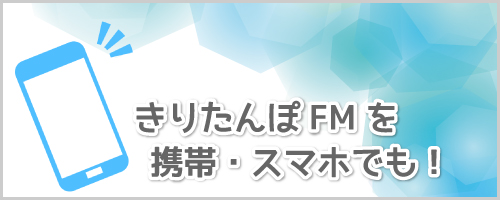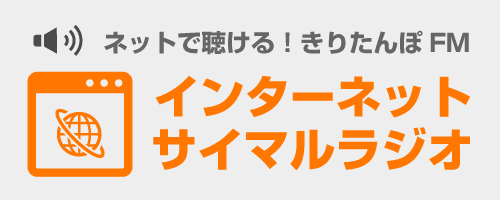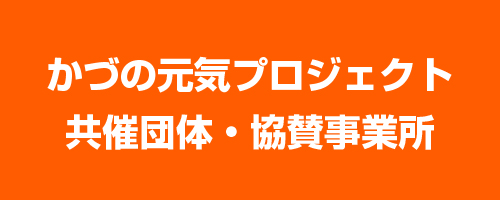織田信長との戦いに敗れ鹿角市大湯に逃れた北畠氏の城の跡、館跡が見つかり、訪れるツアーが行われました。
大湯の市街地の国道から東へおよそ3キロの旧折戸集落には、祖父、父を織田信長に討たれ、この地に逃れた北畠家10代め、昌教(まさのり)の墓が残り、観光地図などでも紹介されています。
山中の深く。長年訪れる人もおらず、近年は、墓はあっても肝心の居城が分からない状況でしたが、去年、歴史の愛好家たちが見つけ、これを訪れるツアーが企画されました。
およその場所は分かっていたものの、入り口を見つけられなかったそうですが、その入り口は、川を渡った先にありました。
24日に行われたツアーでは、参加者20人ほどがおよそ30分、急な斜面を登った先に、南北およそ150メートル、東西およそ60メートルの平坦な、館跡にたどり着きました。
昌斎館(しょうさいだて)と呼ばれるこの館は、北畠昌教がおよそ27年間、暮らしたと言われ、四方を急な崖と川に囲まれています。
参加者たちは本丸の外周を一周し、その広さや、二の丸や土塁の跡などにふれ、感心していました。
参加していた八幡平玉内の折戸塁(るい)さん(45)は、「親戚の集まりになると、自分たちのルーツの北畠の話が必ず出るので、ずっと来たいと思っていた。こんな山深い中に、これだけ広い館を造った努力にふれて、感慨深いです」と話していました。
ツアーを主催した大湯郷土研究会の三上豊副会長(78)は、「日本の歴史にたびたび登場する北畠家が鹿角とつながりが深いことを地元に人たちに誇ってほしいし、こうした遺産を残していきたい」と話しています。
この日は、大湯環状列石の発見につながった「中通り台地耕地整理事業」の、山中にある取水口の跡も訪れ、昭和初期におよそ8キロの水路をずい道などで結んだ壮大な事業と技術の高さに、参加者たちが驚いていました。

(写真はクリックすると見られます)