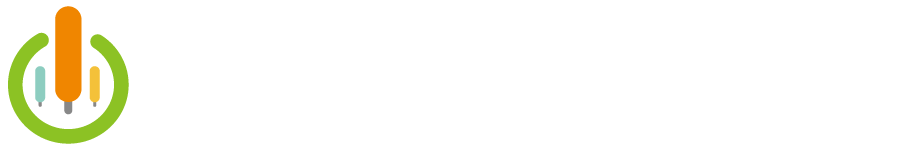地域の平安を願う獅子舞の奉納や、釜のお湯で作況を占う神事が、鹿角市八幡平の神社で行われました。
秋田県の無形民俗文化財に指定されている「松館天満宮三台山(さんのだいさん)獅子大権現舞」が25日、八幡平松館の菅原神社に奉納されました。
この舞いは700年以上前に、菅原道真をあがめて奉納されたのが始まりと言われ、大正時代に途絶えそうになりましたが、昭和12年から神社の春の例大祭で奉納されています。
保存会の会員およそ20人が、修行中の山伏の姿を表す白装束を着て、境内で7つの舞いを奉納しました。
最後の権現舞では、「舞人(まいびと)」が獅子頭を高く掲げたり、獅子の歯を打ち鳴らしたりして、地域の人たちの無病息災などを願いながら舞いました。
また、頭を獅子頭にかまれた人が力を授かるとされる儀式もあり、地元の子どもたちが緊張した表情で頭を預け、「元気に、大きくなれますように」などと唱えてもらっていました。
続いて、釜で煮たお湯をわらの束でかき回して、泡と湯気の立ち方でことしの作占いをする神事「湯立て」が行われました。
湯立てを担った、保存会の川村豊(ゆたか)さんによりますと、「ことしは早く実る品種で豊作になる」という結果が出たそうです。
見守っていた地元の80代の女性は、「みんなが健康で、コメがたくさんとれるようにとお祈りしました」と話していました。
保存会の似鳥吉栄(よしえい)会長は、「ことしは湯立てと権現舞の担い手が代替わりしたが、うまくできたのが一番の成果だ。みんながマルチに役割を担えているので、若い世代も呼び込みつつ、継承していきたい」と話しています。

(写真はクリックすると見られます)