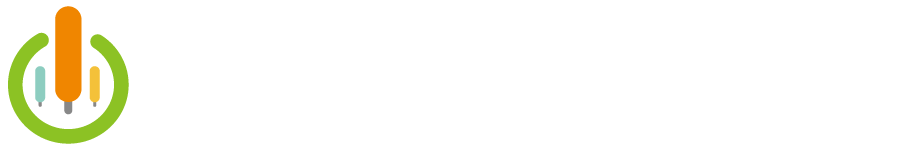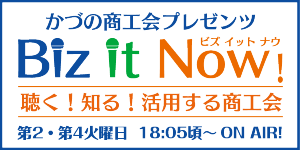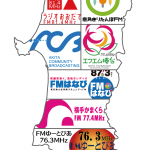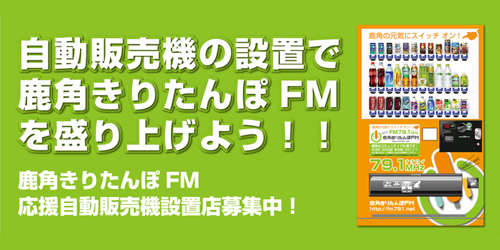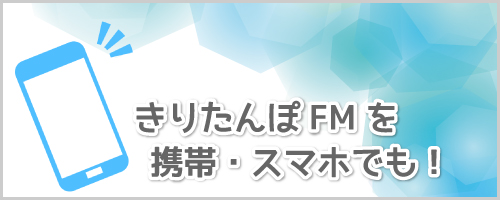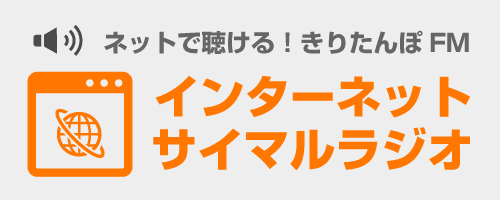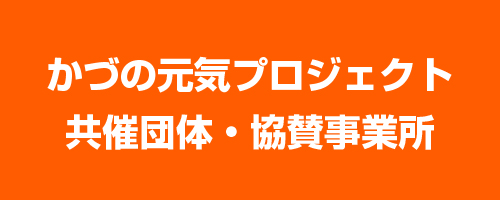鹿角市毛馬内の守り神と慕われる神社の例大祭が始まり、子どもたちの神楽の奉納などで、地域の平安を祈りました。
毛馬内の町の西およそ4キロの、月山の中腹に建つ月山神社は、平安時代の807年に坂上田村麻呂が奥州の平安を願って建立したと言われ、毛馬内の総鎮守と慕われています。
例大祭の起源は分かっていませんが、江戸時代中期の1765年にはすでに、花輪ばやしと1年ごとに交互に行われていたことが古文書に書かれています。
現代では毎年7月12日と13日に行われていて、その最初の行事がことしも12日、市の文化財に指定されている神社であり、地域の人たちおよそ40人が集まりました。
神楽「浦安の舞」の奉納では、巫女姿に着飾った地元の小学生4人が舞姫を務めました。
4人は扇で顔を隠すようにしながら神棚の前に現れると、厳かな雰囲気を表現しながら、鈴を鳴らしつつゆったり舞っていました。
舞姫を務めた小学5年の女の子は、「間違えないように気をつけて踊りました。来年もちゃんと練習して、うまく踊りたい」と話していました。
また参拝していた70代の男性は、「1年間、無事に過ごせたことを神さまに報告しました。町で人が減っていますが、祭りでも、盆踊りでも、みんなでできることを頑張りながらつないでいきたい」と話していました。
例大祭は13日まで行われ、市の文化財の獅子舞やみこしが市街地を巡るほか、目ぬき通りに露店が並び、かつての城下町がにぎやかになっています。

(写真はクリックすると見られます)